SNSで友達や他人の充実した生活や成功している様子を見て、つい妬んだり、落ち込んでしまったことはありませんか? 私も、かつて同じように悩んでいました。
実は、私は小児がんの治療の副作用で、成人しても身長が130cmしかありません。そのため、周囲と自分を比べてしまい、強い劣等感を抱くことがありました。しかし、さまざまな工夫を通じて、次第に自信を取り戻し、自分の価値を見出せるようになりました。
「どうすれば、人と比べることに振り回されずに生きられるのか?」
その答えを見つけるために、これまでの経験をもとに 『比較のストレスを減らす方法』 を紹介したいと思います。
この記事は、小児がんの治療による副作用からの挫折経験を基に執筆しました。個人的な体験として参考程度に読んでいただけると幸いです。
比較の理由
SNSを開けば、友人や有名人の華やかな生活が目に入り、職場や学校では成績や評価を通じて、無意識のうちに自分と周囲を比べてしまうことがあるでしょう。
こうした比較は、時には向上心を刺激することもありますが、過度になると「自分は劣っているのではないか?」という自己否定につながることもあります。
では、なぜ私たちはここまで「他人と比べること」に囚われてしまうのでしょうか? その背景には、自信のなさや承認欲求、社会の仕組みなど、さまざまな要因が関係しています。
ここでは、人が比較をしてしまう理由について説明します。
1.自信のなさが比較を生む
「資格やスキルの習得を目指すとき、『自分が成長したいから』ではなく、友人や家族にスゴイと思われたい という気持ちが動機になったことはありませんか?
また、SNSで友人が恋人と楽しそうにしている写真を見て、『自分は魅力がないのかもしれない…』と落ち込んだ経験はないでしょうか?
このように、自分自身の価値を自分で認められず、他人と比べることで確認しようとする心理 が、比較を生む大きな要因のひとつです。
特に、自分に自信がないと、無意識のうちに 『他人の優れているところ』 ばかりに目がいき、自己評価を低くしてしまいがちです。」
2.承認欲求の強さ
他人の評価
SNSや学校、職場などで、自分の発言や発信に対して否定的な意見が返ってくると、必要以上に落ち込んでしまうことはありませんか?
これは、他人からの評価を強く気にしているから こそ起こる現象です。人は、自分の価値を確認するために、周囲の反応を基準にしがちです。特に、承認欲求が強い人ほど、ポジティブな評価が自信につながり、ネガティブな評価が自己価値の低下に直結してしまいます。その結果、否定的な意見を受けたときに、『他の人はどう評価されているのか?』と、他人と比較することで自分の価値を再確認しようとします。
他人との勝負
テストの点数や成績を気にしすぎて、他の生徒や同僚とつい比べてしまうこともあるでしょう。これは、『勝ち負け』にこだわりすぎると、どんな場面でも『他人より上か下か』を気にしてしまい、比較の罠にはまることが多くなる からです。本来、他人と比較せずに自分の成長を楽しむことが大切ですが、承認欲求が強いと、それが難しくなってしまいます。
3.社会生活による比較の助長
インターネットの普及
現代社会では、インターネットやSNSの普及により、他人のフォロワー数、容姿、スキル、学歴など、優れた点を簡単に確認できる環境 になっています。
その結果、常に自分より優れた人の情報を目にする機会が増え、『自分には何もない』と錯覚してしまうことがあります。
特に、SNSでは多くの人が自分の成功や魅力的な瞬間を発信 するため、それを見た側は無意識のうちに『他人と自分を比べる癖』がついてしまうのです。
社会の価値観
社会には『これが正しい』とされる価値観や流れがあり、それに沿わないと周囲から浮いてしまうことがあります。例えば、みんなが塾に通っている中、一人だけ自宅学習をしていると、『大丈夫?』 『なんで塾に行かないの?』と心配されたり、不思議がられたりする ことがあるでしょう。このように、多くの人が同じ行動をしている環境では、『自分も合わせなければならない』と感じ、自然と比較してしまうのです。さらに、コミュニティ内での比較も、社会的比較の一因です。例えば、同じ趣味を持つ人たちと交流する中で、自分のスキルや知識を他のメンバーと比べてしまい、『このグループの中で自分はどのレベルにいるのか?』と気にしてしまうことがあります。こうした社会的比較は、コミュニティに馴染もうとする心理の表れでもあり、私たちが日常的に比較をしてしまう理由の一つです。
4.自分の軸がない
周りの友人が恋愛を充実させていたり、楽しそうに過ごしている姿を見かけると、つい焦りを感じてしまうことはありませんか?また、同年代のインフルエンサーが成功している姿を見て、『自分は何をしているんだろう…』と不安に駆られることもあるでしょう。このように、自分の人生にとって何が重要なのかという軸がないと、他人の幸せや成功が過度に気になり、つい比較してしまう ものです。特に、目標が定まっていないと、『あの人はすごい』『自分は遅れているのでは?』と感じやすくなります。また、スポーツや仕事の場面でも同じことが起こります。例えば、チームのエース選手の活躍を目の当たりにして、「自分なんてまだまだだ…」と落ち込んでしまうことはありませんか?完璧を求めるあまり、無意識のうちに自分よりもスキルや実績が上の人とばかり比べてしまい、いつまでも満足できない状態に陥ってしまう こともあります。しかし、本当に大切なのは他人との比較ではなく、自分自身の成長です。他人の成功に振り回されるのではなく、自分が人生で何を大切にしたいのかを明確にし、過去の自分と成長を比べること を意識すると、余計な焦りや不安を減らすことができます。
人と比べてしまうことへの対処方法
「SNSで誰かの成功を見て気分が沈んだ」、「同僚と自分の仕事ぶりを比べて自信をなくした」――このような経験は、多くの人が持っているはずです。しかし、比較すること自体を完全になくすのは難しいものです。なぜなら、比較は社会で生きる上での自己評価の一部として自然に行われるものだからです。では、どうすれば「比較によるネガティブな影響を減らし、前向きな気持ちを取り戻すことができるのか?」そのためには、比較の原因を理解し、それに対する具体的な対処法を実践することが大切です。ここでは、比較のストレスを軽減し、より自分らしく生きるための方法について紹介します。
1.SNSや環境の影響を減らす
SNSの制限
SNSは、友達や他人と気軽にコミュニケーションを取れる便利なツールですが、スキルや資格、学歴、プライベートなど、成功している部分が多く投稿される場所でもあります。そのため、他人の投稿を見続けることで、『自分にはないもの』ばかりが目に入り、無意識のうちに自己嫌悪を感じてしまうことがあります。このような影響を減らすためには、SNSの使い方を見直すことが大切です。例えば、SNSは「ゲームや商品情報、ファッションのトレンドなど、明確に知りたい情報があるときのみ検索する」、「お気に入りのインフルエンサーやチャンネルだけを見る」といったルールを作ることで、無意識にSNSを開く習慣を減らすことができます。
SNSの代替
SNSを暇つぶしの手段として使うのではなく、Prime VideoやHulu、Netflixなどの動画配信サービスを利用するのも有効です。SNSは「個人が自分の成功や優れている点を発信する場」ですが、動画配信サービスは「映画監督やプロデューサーが、視聴者に感動や楽しさを届けることを目的として制作しているコンテンツ」です。これにより、他人と比較せずに純粋にエンターテイメントとして楽しむことができるでしょう。
距離感の意識
過度に劣等感を抱いてしまう相手とは、適度に距離を取ることも重要です。例えば、常に競争意識を持たされる環境にいると、自分の価値を過小評価しがちです。もし、特定の人と接することで強い劣等感や嫉妬を感じる場合は、無理に関わり続けるのではなく、自分の気持ちが落ち着く距離感を見つけることが、自信を保つために役立ちます。
2.自分に目を向ける・自己肯定感を高める
常に他人と比較していると、嫉妬や焦燥感が生まれ、心に負担を感じることが増えてしまいます。このような状況を変えるためには、他人ではなく、自分自身に目を向けることが大切です。具体的には、『今日1日でできたこと』を日記に書く習慣をつける のがおすすめです。例えば、「英単語を3つ覚えた」、「プログラミングの基本が分かった」、「家の片付けを少し進めた」など、どんなに些細なことでも構いません。そして、毎日書いた日記を1週間後や1か月後に振り返ることで、他人ではなく過去の自分と比べる視点 を持つことができます。これにより、『以前はできなかったことができるようになっている』と実感でき、自己肯定感が向上し、心に少し余裕を持てるようになるでしょう。
3.価値観や視点を変える
成功の裏での努力を知る
他人の成功や幸福の裏には、想像以上の努力が隠れていることが多いのではないでしょうか?しかし、最終的な成果ばかりに目を向けてしまうと、その人がどれだけの時間をかけ、どれほどの苦労を乗り越えてきたのかが見えず、『自分とは能力が違う』と落ち込んでしまうこともあります。このような比較を防ぐためには、他人の結果だけでなく、その過程にも目を向けることが重要です。例えば、成功しているインフルエンサーの苦労したエピソードを調べてみたり、恋愛や学業で成果を出している友人に「どんな努力をしたのか?」を聞いてみることで、成功までの道のりをよりリアルに知ることができます。そうすることで、『最初からすごかったわけではなく、努力を積み重ねた結果なのだ』と気づくことができ、過度な比較を避けられるでしょう。
自分の人生軸を持つ
世間の価値観に振り回されてしまうと、自分の行動や選択に自信が持てなくなってしまいます。そんなときは、『自分にとって本当に大切なことは何か?』を考え、価値観の軸を持つことが大切です。例えば、「一流企業で活躍すること」、「自分の趣味の時間を満喫すること」、「家族の時間を大切にすること」など、人それぞれ大切にしたいものは異なります。自分の価値観を明確にすることで、周りの意見に流されることなく、自分らしい生き方ができるようになるでしょう。
4.ポジティブな行動を取る
夢中になるものを見つける
余暇時間が多いと、つい他人の充実した生活と比べてしまい、虚無感を感じることがあります。そんなときは、夢中になれるものを見つけることが効果的です。資格の取得やスポーツ、料理など、自分が好きなことに打ち込む時間を作ることで、自然と他人の幸せに目を奪われにくくなります。子供の頃を思い出してみてください。学校の授業中に、好きな趣味や遊びのことばかり考えていたことはありませんか?このように、何かに夢中になっていると、意識が自分自身に向き、他人の生活や成功と比較することが減ります。私自身も、かつて周りと自分を比べて過度に落ち込み、世間の目を気にしながら生きていました。小児がんの治療の副作用で、成人しても身長が130cmしかないため、周囲と見比べて強い劣等感を抱いていました。しかし、プログラミングに夢中になることで、次第に他人のことを気にしなくなり、自分の成長に目を向けられるようになりました。
他者を誉める
他人の才能や成功を妬んでしまうことがある場合は、あえて相手を褒めることも有効です。例えば、「このプレゼン、資料の構成が分かりやすくて良かったよ」など、具体的な行動や成果を評価することで、相手との関係がよりポジティブなものになります。すると、比較によるネガティブな感情が和らぎ、『この人はすごいな、自分も頑張ろう』と前向きな気持ちに変わっていくことがあります。このように、自分が夢中になれるものを見つけ、他人の良いところを素直に認めることで、比較のストレスを減らし、より充実した毎日を送ることができるでしょう。
まとめ
人と比べることは決して悪いことではありません。比較を通じて成長できることもありますし、競争がモチベーションにつながることもあります。しかし、過度な比較が自己否定やストレスの原因になってしまう場合は、意識的にその影響を減らすことが大切です。SNSの使い方を工夫し、自分の成長に目を向け、価値観の軸を持ち、ポジティブな行動を取ることで、「比較の罠」から抜け出し、自分らしく生きることができるようになります。他人の人生をうらやむのではなく、「昨日の自分より少しでも成長する」ことを目標にすることで、前向きな気持ちを持つことができるでしょう。他人との比較ではなく、「自分がどのように生きたいか」を大切にしながら、より充実した毎日を送っていきましょう。

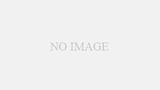
コメント